「定期テストで結果を残したい」「定期テストの勉強の仕方がいまいち分からない」という方も多いのではないでしょうか。
しっかり勉強したつもりで臨んだのに全くいい点数が取れなかった経験もあると思います。頑張ったのに点数が取れないとやる気がなくなってしまいますよね。
頑張ったのに点数が取れない人はもしかすると努力の方向性が少しずれてしまっているかもしれません。定期テストは正しい方法でしっかり努力すれば誰でも成績を伸ばすことができます。
私自身、中学生の頃はほぼ全ての定期テストでトップの順位を保っていました。それは定期テストで点数を取るための対策が身についていたからだと思います。
特に中学生にとって定期テストは内申点に直接つながるテストです。内申点は公立高校の受験の際にも提出されるため実質、学校の定期テストから受験が始まっているといっても過言ではありません。
今回は、私が実践していた学校の定期テスト対策をご紹介したいと思います。主に中学生向けに国語・数学・英語・理科・社会の5教科をメインに解説していきます。
全ての教科における対策の前提
まずは、定期テストにおいて教科に関係なく大事な点についてお話しします。
それは、「問題を作成する人と実際に授業をしている人が同じ人である」ということです。固い表現になりましたが、つまり教科を教えている先生本人が定期テストを作成しているということです。
当たり前のように聞こえるかもしれませんが、受験における筆記試験やその他資格のテストなどは問題を作っている人がどこの誰か分かりません。
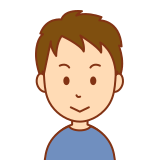
つまり何が言いたいの?
つまり、学校の先生が直接教えていないことは定期テストで出てくる可能性が低いということです。例えば、教科書で一部解説を飛ばして次に進むようなことがあると思います。こういった場合はその範囲からテストに出題される可能性がかなり低くなります。ですので、学校の先生が説明を省略したりあまり深く解説しなかった部分は「定期テストには出しませんよ」という意図がある可能性が高いです。
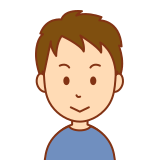
普段の授業からしっかり話を聞くことが大事だね。
その通りです。私は普段の授業で先生が特に強調して説明しているところやあまり触れなかった箇所をしっかり教科書などにメモし、定期テスト対策に繋げられるようにしていました。
「ここはあまり勉強しなくていい」という部分が少しでもあれば、その分他の勉強に時間を費やすことができます。
また、当たり前ですが授業の板書で特に強調して書いていたことはテストに出題される可能性大です。先生がテストに出しますオーラを出しているはずなので敏感に感じ取りましょう。
教科別の対策方法
ここからは教科別の対策方法について解説していきたいと思います。
数学
数学は授業で習った公式などをしっかり定着されることが大事です。学校のプリントやワークでやった問題が数字を変えて出題されたりするため、対応力が求められます。
それらのプリントやワークを繰り返し解くだけでなく、ネット上などで似たような問題があればそれも解いてみましょう。計算問題などを深く考えることなくスムーズに解けるようになるのが目標です。
ワークやプリントの解き方ですが、初めの1周目などはしっかり紙に計算を書いて解いてみましょう。2周目、3周目以降は目で見て解き方が最後まで頭で分かれば次に進むというように、書く時間を減らしてより多くの問題に触れられるようにしていました。
また、数学の先生は特に100点を取らせないような難しい問題を出してくることがあります。そのような応用問題への対応策はワークに載っている応用問題をしっかり理解し解けるようにしておくことです。例えば、問題でABの長さを求める問題が出ていたら、ABではなくBCを求める場合どうしたらいいかなど、自分で問題をアレンジして勉強していました。
逆に90点以上などの高得点を目指さない人はそういった応用問題に時間をかけすぎずに他の問題に時間を割くことを考えましょう。
国語
国語についてはどうのような対策をすればいいか分からない人が多いかと思います。
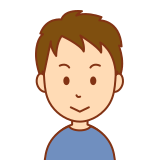
漢字の勉強は分かるけど、文章問題は何が出るか予想できないから
対策は難しいんじゃないの?
確かにそう思うかもしれませんが、文章問題でもしっかり対策はできます。
まずは、授業でやった物語などの文章を全て頭に入れておくことです。基本的に国語の問題は何の文章が出題されるかはあらかじめ分かっていると思います。
文章をだいたい頭に入れておくことで、試験時間で文章を改めて読み直す時間を省略できるということです。文章が頭に染みついていれば問題を見た時に、どの辺りに答えがありそうというのがすぐ分かるようになります。
もう1つは、ワークの問題を解きこむことです。国語の先生にとっては問題を作るうえで先生自身の解釈を入れてしまってはいけないので、既にワークなどに載っている問題から出題する方が安心です。そのため、ワークの問題からそのまま出たり、少し変えて出されたりすることが多いです。
もちろん、漢字は習ったものから出るので一番点数を取りやすいはずです。漢字の部分は確実に満点を取れるように対策しましょう。
英語
英語についても国語と同様、教科書で扱った英文から読解問題が出されることが多いと思います。一部、オリジナルの英文問題も出されるかもしれません。
教科書で扱った文章はテスト中に読まなくてもいいように何度も音読して頭に入れておきましょう。その上で、新しい単語や熟語、重要表現などを意識しながら日本語の意味が同時に出てくるようになるまで読み込みましょう。
そうすると、テストで単語や熟語の意味、並べ替え問題が出た時でも難なく解くことができます。特に新しい文法を習った際にはその部分が並べ替え問題や穴埋め問題として出題される可能性が高いです。
私は余裕がある時は、教科書の英文を暗記するレベルで何度も音読していました。そのおかげで並べ替え問題が出ても文章を覚えているため、何も考えずに解くことができました。
また、新出の英単語や英熟語は言うまでもなく暗記必須です。意味さえしっかり覚えておけば選択問題や穴埋め問題などどんな形で出されてもある程度対応できるはずです。

理科
理科は問題演習として学校のワークや演習プリントを何度も解くことが大事です。
先生によってはワークからよく問題を出すのかプリントから出すのかなど事前に教えてくれる場合もあるのでしっかり聞いておきましょう。
スムーズに解けるようになったら選択問題を選択肢を隠しながらやったりするとさらに理解度が深まります。
また、理科室で実験を行った場合はしっかり内容を復習しておきましょう。実験をするということは、大事な内容であるとともに生徒の理解も深まっているだろうと認識されています。
社会
社会も理科と基本的に同様ですが、ワークでの演習がメインになってきます。
歴史の場合は様々な人物が出てくると思いますが、登場した年代の順番も意識することで問題が解きやすくなります。例えば江戸時代後期の改革について、徳川吉宗(享保の改革)→松平定信(寛政の改革)→水野忠邦(天保の改革)といった順番で覚えるということです。
歴史では特に年号を並べ替える問題が頻出されるため、様々な出来事や人物について年号で覚えることは定期テストだけでなく受験のためにもなります。自分なりに語呂や歌を作って覚えると記憶に残りやすくなります。
また、社会の先生によっては教科書の内容だけでなく、最近のニュースを使って問題を出す人もいるかもしれません。先生が授業でちらっと言っているかもしれないので普段の授業からしっかりノートを取っておきましょう。
まとめ
今回は定期テストの対策法を教科別に紹介しました。
これらの対策法はあくまで一般的なものになるので、学校の先生の出題傾向などをつかみながら慣れていくことも大切です。
冒頭にもお話ししましたが、定期テストは受験で必要な内申点に繋がる大事なテストです。ただのテストと甘く見ずに毎回の試験を全力で行いましょう。
他にも普段の勉強に役立つ有益な記事をお届けしていますのでぜひご覧ください。
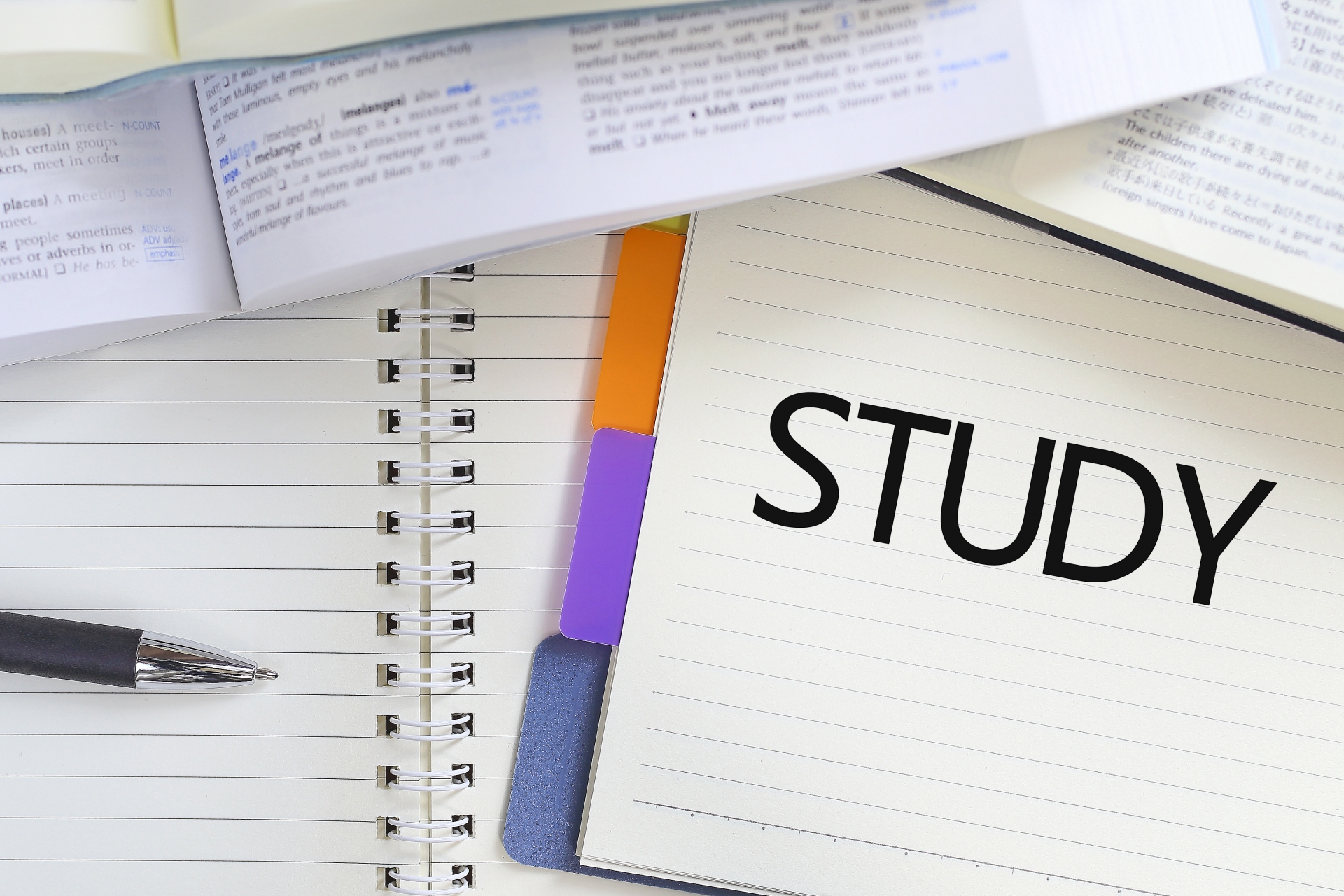

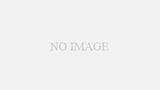
コメント